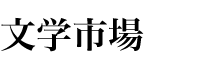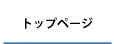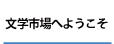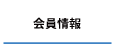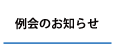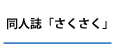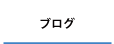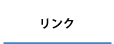2025年10月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:10月19日(日)
- 例会出席者:5名
ミヤコワスレ
ミヤコワスレは、花というとあまりピンとはきませんが、草花というとなるほどとうなづけるところのある「花」です。つまり派手過ぎず、地味過ぎず、共感を誘います。そのタイトルから、その「思い」みたいなものを「そっと」置いている作品です。普通の家族の、67歳になるお義母さんの、その終末を書かれた作品なのですけれど、その描写の仕方、子供達や孫たち、近くの親戚や、遠くの親戚、たいへん多くの血縁者を登場させ、「おわり」を見送った作品でしょう。ですから、場面はとても広範囲なのですが、視点となるものがなんとなく神的、仏的なのかもしれませんし、屈託なくいえば「心」視点なのかもしれません。作者の物を見る力には感服しました。
山羊
とてもシュールな作品で、面白いです。面白いけれど、難しくて、ああーじゃない、こうじゃないと類推して理解しようとするのですけれど、さて…難しいのです。〈僕は、山羊のような耳を持って、安全を謳い文句として生きる〉のが、山羊のようになった「僕」で、その見たものなのか、それと同時に山羊になった僕のあれこれなのかなと、とても楽しく読ませていただきました。この作品はとても短いのですけれど、読んでいると、本当はとても長い作品・何日も何日も見送った末に辿り着いた心の休憩場所で、そのいくつかの出来事をポケットから出して書かれたのかなと思いました。大山さんは、いつも、とても奇抜な作品を書かれますね。
ハン・ガンのこと
ノーベル賞というものに、それほど注目はしてきませんでしたけれど、ハン・ガンという女性作家の、その文学性に、このように心を込めたものを目にすると、なるほどと思います。なるほどと思いながら、どこかしら、ハン・ガンと青木朋さんの「文体」のようなものを、似ていないかなと感じたり、似ていると感じたりしながら、とても興味を持って読ませていただきました。すごいなあ、と思い、感じたりもしました。それはハン・ガンのことでもあれば、青木さんの文章・文体のことでもあります。ノーベル賞とはいかなくとも、何らかの文学賞に応募されることをお勧めします。感想文なのですけれど、そこに文学性のようなものを感じるのです。
読書雑記 60
SKさんは、このコーナーを楽しみにしつつ、書かれているのだなあということが、細部から感じられます。身も蓋もありませんが、それを「★印」の数からうかがい知れます。これまで、ずっと、通信簿ではありませんが、星の数は通信簿の点数なのだとばかり信じていました。それが、そうではないことが、やっと、わかりました。★印が5つの作品よりも、★印3つの作品の方の「コメント」が多いという場合が、ここのところ多々見受けられます。杓子定規の点数ではない、それとは別の視点みたいなものがあるのでしょう。『ある旅人一座の記録』(?)とか、『ゴッド・ファーザー』みたいな映画を、みたいと思うこの頃です。
愛 文
読者に伝えるべき情報は伝えずに、迷路になった道筋を「迷路、迷路、迷路…」と綴った作品なのではないかと、読み終えました。もっとも、難解なので読み終えたという心持にはなりませんでした。作品を難解にしているのは、『あなたのことを愛っています』で、その内実に入らないまま、別物であるかのような道筋が展開されていき、「呪文」の中に消えて行くのです。もしかしたら、作者は「特異」な作品を書いてやろうと思い、挑戦したのかもしれません。その点では、確かに特異で、成功しています。無い物、存在しないものを書こうとされたのか、または、自分の内なるものを見つめて書かれたのか、難解ですけれど、わからない面白さは充分にあります。
うつろ
すごく考えられた作品で、作者の描写してとらえる力に感心しました。そして、タイトルが「うつろ」というのも、なんとなく、目の前に書きたいものはあるのだけれど、それは〈うつろ〉でぼんやりと形が歪んであるだけなんだ、というような、命やなにかの日常に埋もれて、作者が何かを手放しているようなところが、「うつろ」といいながら確かに魂としてあるのです。そういったことが神田川なんだと済ませられるといいのですが、なかなか大変です。神田川とは何かと考えますと、神は神です。田とは米の生まれるところです。その神と米は、どうしたって人間にはなくてはならないものです。この作品には、その人間が書かれています。
夏の日の午後
~高校生探偵の迷推理~ということで、高校生だと思い読むのですが、変に大人っぽさを感じてしまうところがありました。その一方で、殺人事件なのですから、大人の社会性みたいなものも必要なのだろうし、高校生の立場としては「楽しく・面白い」作品が要求されるでしょう。ということで、高校生であること、殺人事件の「解決」と、二つのことを両立させる難しさがあるのかもしれません。作者の頭の中には、高校生がいて、それとともに、作品を書く者=作者がいます。ほとんどのところで、作者の存在は消されていますが、やや、その影みたいなものが残っているかもしれません。もっとも、小説には「若さ」が欠かせませんから、サービス的にはオッケーなのかも。
未完成 1
今回の『未完成 1』は、読み終わって納得したのですが、佐木笑美のことが書かれ、パチスロのことが述べられ、明日は競輪にいってきます、とのご挨拶で短い幕をおろしています。なかなかの万歳三唱ものです。でも、それは二十五年も前の話なんですね。なぜか深大寺、やぼったいかぎりの女だった佐々木笑美、その彼女がなぜか…頭の中にカミナリが落ちたのか、目が離せなくなり、このまま彼女と手をつないでいっしょに家に帰りたいのですが、頭も、心も、もはや自分のものではない……では誰の物かといえば、もう、佐々木笑美さんの物です。だけれど、末尾の「ぼくたちの降りたブランコだけが揺れていた」は、過ぎ去った時間の思い出です。