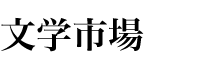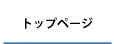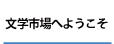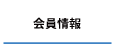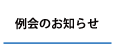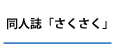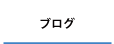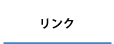2025年9月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:9月21日(日)
- 例会出席者:8名
鼓膜
冒頭の二行、「自分の鼓膜を見るのは初めてだった。思いもよらない事だったが、彼は自分の一部に見ほれた」と、とても不思議な幕開けをします。これって、西洋絵画にある、鎧を着た武者が自分の首を小脇に抱えて立っている、その絵に似て、シュールです。二十年前、二十年前、二十年前、二十年前、と反復が四度あるのも意味深で、医者が女性で彼と同じ三十七歳も偶然なら、ライブハウスの店長も三十七歳の女性であるのも、なんとなく存在の反復を感じさせます。不思議だった、あれほど印象的だったのに、彼女を思い出したのは二十年ぶりなのです。……と、その彼女がまだ鼓膜の奥の闇の中に、じっと潜んでいる気がした、と……現在完了形です。
サプライズデリバリーサービスの裏と表の間側
〝SOLDOUTまで残り一個〟と、それに飛びついても、その一個は確かに売れ切れにはなるが、すぐに別の同じ商品が現れて〝SOLDOUTまで残り一個〟は反復されるのです。それが「サプライズデリバリーサービスの裏と表の問題」なのです。つまり、このような宣伝って、考えて見ればすべてに当てはまるのではないでしょうか。というのも、よくよく考えれば、世の中が回っているのはこの単純なことの反復なのですから。それにしても、注文者が住所を偽っていても「特別な箱」があなたのおうちにやってくる。…は、怖いですね。タイトル末尾の「間側」って、もしかして裏の顔ってことなのかどうか?
うなり
兵斗は「うう、ううう」とうなるのです。こういったことは、言葉足らずの幼い子供にありがちな振る舞いなのですが、そのことに明確な輪郭線を引くことによって、言葉だとか、自分の存在とかを、それって何なのかと追及された小説なのではないかと、受け取りました。こうしたことって、一般的には、人間関係に疎いために生じる現象だと思われがちですが、もしかすると、人間関係に敏感過ぎるがために生じる不協和音なのかもしれません。「ううう、うう」と言葉を発しようとするが、それが「音」にはなるが「言葉」にはならない。その苦しい場面を見極めて書かれています。無の一点を見つめて、作品を構成するってすごい胆力ですね。
母
とてもよい詩だなと、ぼんやりながめていたら、「母」という字がほんとの母のように見えてきました。どのように見えたかといいますと、母という字の囲いが、お母さんのお腹のように見えたのです。そして母の字に横線がありますけれど、女の子が「、」とあらわれ、二女が「、」と、続くのです。そのようなものだと、たんに思っていましたけれど、一個の文字に深くこだわったことはありませんでしたから、立原さんのこの詩を読んで、つくづくと、「人」というものを感じました。冒頭の「働いて」の三行は、当初、人間の苦行のように受け取りましたけれど、苦しいけれど、その苦しさがもたらす営みで、それで家族は成り立っているのだと、……。
諦めなければ
冒頭の三行、二連目になると二行に減じ、三連目では四行に膨らんでいる、短い端正な詩です。この作品を読んでいて感じたのは、「自業自得」という言葉です。いろいろな人間の成すことが、次から次へと絡まってゆき、さあ、いよいよどうにもならなくなった、という「時」に、術はあるのかどうか。そして、その時期はいつなのか。欲望はあきらめるべきで、希望は持つべきなのですが、ぜひ、そうなって欲しいものです。
終点を置く
なんとなく〈随筆+小説〉のような印象を受けました。特に「置く」という言葉に客観を感じ、ある西洋絵画を想起させられました。その絵は騎士が鎧をまとっていて、小脇に、なんと自分の生首を抱えている絵なのです。かなり有名な絵なので、皆さんも一度は目にしているのではないでしょうか。ということで、年金にまつわる話なのです。損をしているのか、得をしているのか、わからないような計算=年金計算のあれこれをして、自分で自分の命のことを算段する滑稽さと悲しさを、読者は実感するのです。年金というのはありがたい仕組みなのですが、それの出どころは「自分の財布」だということを、半ば忘れてしまってのことです。
映画日記 70
いつもすごいですね。4ヶ月間で「47本」の映画を観るなんて、実にすごいです。その中で、★印5つの作品が2作品あったというのも、充実した映画鑑賞だったのではないでしょうか。その2つの作品は、『聖なるイチジクの種』と『ファーストキス 1ST KISS』です。『…イチジクの種』は判事に昇格する寸前の父の顛末ですが、自らが禁固刑を受けてしまうのです。次の★5つの作品は『ファーストキス』です。こちらは日本の作品だからなのでしょうか、★5つながら、作者のコメントは控えめです。コロナ禍か治まりよかったと思うのですけれど、劇場等々へ足を運ぶ観劇者が、まだ戻っていないように感じます。戻るといいですね。
野草迷走・山芍薬
高尾山の植生の種類は、日本ではなのか、世界においてもなのか、最も多い山なのだと伺っています。高尾山の南側には暖かさを好む植物が、北側には寒さに強い植物が自生していて、その多様さでは世界有数だと伺っています。日本列島の北と南の分岐点なのでしょう。そんなところに、日曜日ごとに行き、その自然を満喫されているのですから、さぞかし、健康的にも精神的にも万々歳の日々ですね。私も、大学に入学した年に、1年程、高尾で暮らしたことがあります。そのころは、今と比べると登山者は少なかったと思います。今はだめみたいですけれど、高尾山から下山して尾根伝いに天皇御料まで、なんども歩きました。(今は御料までは行けないみたいです)