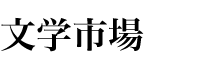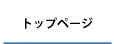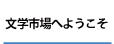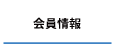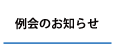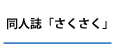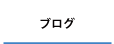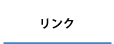2025年7月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:7月20日(日)
- 例会出席者:7名
雑記とエッセイ
非常にコンパクトなエッセイの「3題」です。はじめの「1題」目はとても控えめで、そのお題がありません。ないのですけれど、一行目で、しっかりと、「切れ痔である」と告白されています。それにしても、松尾芭蕉も芥川龍之介も夏目漱石も痔だったとか、それはよいとして、早く治るとよいですね。庄野順三自分の身辺を題材にして書いているとか、でも、純文学作家って、たいていそうなのではないかと思います。さてはて、三題話の締めくくりは「僕のパチスロ体験」なのですが、ゲーム台と格闘するかのような熱の入れようで、盛り上がっているのか、それとも単に熱くなっているのか、読んでいるこちらが、勝てますようにと、ついつい、応援してしまいます。
ベッドで寝ていた
とても不思議な小説です。笠原知佳と幡野先輩と蛇との、奇妙な小説です。笠原知佳と幡野先輩と、それと対等に置いてよいのかどうかわかりませんけれど蛇、その三角関係のごときものがこの作品なのではないでしょうか。蛇がどのような役割を果たしているのかわからないのですが、スルスルスルと橋渡しをするともなくして、不完全だった笠原知佳と幡野先輩との関係に実質を成させるのです。ということで、本当はすごく怖い話なのに、その怖さを作品世界に解消させて何事もなかったように終わらせる表現にはびっくり、というか、感心しました。「せんぱーい。夕飯どうしますか」のフレーズは、とてもよいですね。どこか無音の呼びかけのように聞こえます。
うちなるものは
とても奇抜な作品です。高校生の頃に思いを寄せていた女性と再会し、そのころの気持ちを大切にもっていたけれど、その気持ちが伝わらないのです。再会した時には、私は図書館の館長になっており、いわば、良き人生を全うしつつあります。そして、その女子である梅元さんは司書教諭の資格を持っているのですけれど、高校生の時のバスの事故で左大腿骨骨折を負ってしまったのです。事故の後遺症を負った梅元さんと、図書館長という、それなりの地位についている聡志との間のバランスがいかようなものなのか、梅本さんの気持は、聡志への思いを持っていたとしても、相いれられるものはないのかもしれません。
ノスリ
具象的な作品なのですが、その具象が抽象に包まれていて、それを判読するのはやっかいな作品だなと感じました。はじめは小さな「・」に見えたと始まり、直ちに「一羽のタカだった」となるのですが、ノスリからタカへと成長する物語が、それは秋から冬へ、そうして冬から春への必然的な物語であり、ノスリのタカへの変身です。合戦になれば→…雪が降る→老木の低い声が/こだまのように社殿の林に響いた、とありますが、これは「合戦」の模様の描写ではないかと感じました。こうしたことを通して、ノスリからタカへと成長するのが里山の掟みたいなもの、何度も繰り返された物語なのかもしれません。とても長い詩で、どこか「長命」の祈りのように感じました。
郷里日田への旅
作品に入る入り方は人それぞれなのでしょうけれど、作者の「あいさみこ」さんは独特の入り方をされるんだなと、今回、つくづく感じました。何種類もの入り方があるのだ、というようなものではなく、いつも自然体で入っていける何かをお持ちだということです。おそらく、ブルガリアにいても、東京にいても、大分にいても、きっと同じなのではないだろうかと感じました。どこにでも自然体で自分を出せる特技をお待ちなのでは? 天性のものなのか、それとも人との交流で獲得したものなのか。〈あいさみこ〉さんの書かれる文章・文体は、前へ前へと進みます。とても力強いです。ブルガリアの美女のダンスは、劇場でも、作者の自宅でも拝見、とても記憶に残っています。
おじいちゃんのたからもの
「まいちゃん、ちょっとすごい画家を発見したんだよ」と、おじいちゃんは小学六年生のわたしを上野の美術館で催している展覧会に、誘います。そこには沖縄の画家・田中一村の画いた奄美大島の絵が飾ってあったのです。感動したおじいちゃんは、三連休を利用して奄美大島に行き、いっぱい感動して帰って来ました。その感動がどんなことなのか、わたしにはわからないのですけれど、おじいちゃんの顔を見ると、とてもすばらしいものだということがわかるのです。おばあちゃん、そしてママ…。さて、おじいちゃんのたからものは何でしょうか。それはとても簡単な答えです。おばあちゃん、子供達、孫達の元気な笑顔が宝物なのでしょう。命です。
等身大人形預かります
人形を、おそらく美人であろう人形を一週間預かるという仕事を請け負うのですが、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜と、一週間が経過して作品はそこでおわってしまいます。作品の「意味」みたいなものを捕まえることができないままに、読み終わってしまったのです。これではいけないと思いつつ、考えるのですが……はじめ良ければ終わり恐しです。「無事に食べられれば、それは予定通り二十二食めになる見込みだ」はとても怖い終わりです。一週間前にあった部屋と、一週間後の部屋とは、まったく別世界のような描写になっています。そのことを推察すると「時間」の存在もあやふやになり、一週間はほとんど一生のことなのでしょうか。
GS会館
GS会館と書かれて…ニュー新橋ビルといわれると、ああ、あの大きな雑居ビルのことかなと思いつくのですが、確かなことはわかりません。当時としては、とてつもなく大きな雑居ビルで、あまり奢った所もなく、庶民的・市民的だなと感じていました。とはいえ、現在でも存在しているのですから、文化かなとも思います。この作品からも伺われますが、なぜか、なじむような雰囲気があるビルで、腰が引けるような威圧感は皆無です。とても鷹揚な時代で、叩かれて落とされても、苦にすることはなく、すぐに立ち直れる時代だったと記憶しています。ニュー新橋ビルの淳喫茶の巨大さも、私が知っている店では一番でした。
読書雑記 59
なぜか、今回の読書雑記は、読みごたえがありました。「ゾンビのおぞましさは、言葉が通じないことだ」と書かれていますが、ゾンビと言葉が通じないって、とても幸いなのではないかと思いました。ただ偉大な作家生活には病院生活が必要だ、はパスしたいところです。坂本龍一さんはせん妄に悩まされたのですか。人生を100%満喫したのではなかろうかと思っていたのに、同姓として、お悔やみ申し上げます。なぜ今回の読書雑記がよかったのか考えてみました。すごく単純なことかもしれません。それは「死」なのかもしれません。死って、文章のおわりにつける「。」なのかも