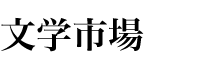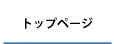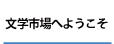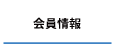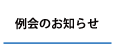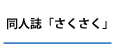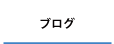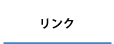2025年6月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:6月15日(日)
- 例会出席者:6名
映画日記 69
今回の映画鑑賞した作品を数えてみましたら、55作品でした。なお、気になって「☆印5つ」ついた映画を数えてみましたら、なんと5作品でありました。そんな中で、安部公房・原作の『箱男』が星印2つなのには、「えっ」と思いました。監督の腕がわるかったのか、安部公房の文学観と、映画監督の感性とがうまく合致しなかったのかもしれないなと、余計な詮索をしてしまいます。ところが映画評を読みますと、安部公房の名を看板にしながら、内容的にはまったく異なった映画だそうで、大作家の映画に星印2つには、映画鑑賞したわけでもありませんが、もやもやしたものがいつまでも残ってしまいました。
孝と広志と案山子
とても不思議な作品だなと思いました。孝と広志の双子の兄弟がいて、孝が兄で、広志が弟です。もちろん、双子の兄弟ですから、そこに兄とか弟とかのきまりもないのでしょうが、どうも、兄や弟といった属性に関してはなおざりにはできない、変わった時代・地域なのかもしれません。弟の広志に見つからないうちに「この案山子」を、人目につかぬところに埋めてしまわなければならないのです。兄の孝は畑を耕しています。弟の広志は町で保険の仕事をしています。さて弟と兄と、どちらが出世しているだろうかと思案するのですが、かなり唐突です。不入斗町にある不入斗橋でのあれやこれやは、なにがなにやらなのですけれど、理路は整然と紡がるのでしょう。
靴墨色の花
不思議な詩篇です。基本的に2連ずつにつながって読めるのですが、9連めの「靴墨の色に」のところで、なぜか逆転しているように感じさせられました。「咲くような」「母印の朱が鮮やかに」「方法が」の3つのフレーズは、どことなく他者的です。「あるような季節」は、「よし」とはしないが、その季節をちゃんと受け入れているよ、といった挨拶なのかもしれません。考えれば冒頭の、「分かれた枝葉の先」は「別れた僕たちの今」というようにとることも出来ます。作者の感性の細やかさには、ただ、すごいなと思います。靴墨色の花って、何の花でしょうか。黒百合なのでしょうか。作者に特別な、秘密の花なのでしょうか。大事な花……。
無くて七癖
今回の梅琴さんの「無くて七癖」を読んで、そうかそういうことか、と梅琴さんのことがわかったような気がしました。とても行動的で、これだ! と思ったことは直ちに実行する。それが梅琴さんだし、梅琴さんなのです。お宅に、文学市場の面々で伺った折、庭のようすなどを見せていただきましたけれど、あのぎゅうぎゅうと詰め込まれた植栽は、いかにも梅琴邸の雰囲気に溢れていて、しっかりと記憶しております。植物、花、庭の造形、池、池の鯉、まあ見事なものですが、なんと言っても素晴らしいのは「奥様」でしょう。いろんなことに頑張って来られた梅琴さん、奥様のお陰なのではなかと思います。あの日、私たちの帰りの乗り物の時間まで気配りされていました。
とぼとぼ行状記
とぼとぼ行状記をトボトボと読んでいったら、ある時から、与謝野鉄幹と与謝野晶子の文学的な優劣の差が浮き出て、そこのところの様々が描写されていて面白かったです。私は一貫して、与謝野鉄幹=与謝野晶子と思っていましたが、当時の世間では与謝野晶子にとって鉄幹は「よけいもの」だったのかもしれません。これは世間の目に焦点を当てるからで、子供に焦点を当てると、ちゃんとした夫婦だったのではないかと思うのですが、いかがなのか。夫婦仲は、夫婦にとっては良くても悪くても、どちらでもよいのですが、子供達にとってはそうではありません。子供達の成長をみるに、鉄幹も晶子も、良き父・良き母だったのでは?(他者からみると、そんなところです)
犬の算数
すごいですね。犬もすごいけれど、ジョニーさんはもっとすごいです。まあ、人間ですからね、と軽くいなされてしまうでしょうけれど、犬をここまで観察する方、または出来る方はそうそうはいません。もっとも犬でも、ジョニーさんの同居している犬のように、頭の良い犬に逢ったことがありません。頭の良い犬というけれど、本当は、接し方しだいでいろいろと変わってくるのかもしれません。犬とはいえ、人間の愛情はすぐにわかるのでしょう。子供が言葉を理解していくように、愛情の意味も、自ずとわかるのかもしれません。「わからない」当方は、分かろうとしないだけなのかも……。ジョニーさんの目の俊敏さは、ほんと、すごいです。
みんなの委員長
タイトルが「みんなの委員長」です。かつて、随分前の時代には、「級長」と言っていました。その後、「学級委員」になって、現在では「委員長」か、単に「委員」なのかもしれません。この作品における「委員長」選びは、とても盛り上がっていて、こんな風な選挙なら、やりがいがあるだろうし、教育的にも、眼に見えない処での〈教育〉になっているのかなあと思います。「委員長」と考えて見て、学級委員として瞼にうかぶのは、失礼ながら[作者のSKさん]です。作品を読むSKさんの「目」は自由自在のスタンスをとっています。作者のコメントしているコーナーで、その作者を持ち上げるなんてことをしたのは、初めてです。
余白
不思議なタイトルだ。目の前のことなのか、過ぎ去った時間のことなのか、そのことはわからないのだけれど、「余白」と提示されている。それは自己の主張というわけではなく、自分から離れたところに自分がある、その自分を「あらわして」いるのかも。内面的なことを書いた作品にしては、とても長いのではないかと思う。たいへんだったでしょう。ほぼ自分の「生きた」ところのあら方を書かれているのだから。タイトルと作品を、うまく理解するために、『余白』とは何か考えるのだけれど、神田川のここで、自分のあらかたの時間を過ごしたということしか思い浮かばず、「余白」の言葉の感情をとらえられませんでした。作者はすばらしい作品を自分に見つけられました。