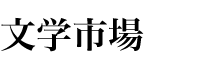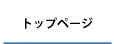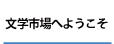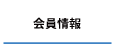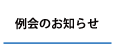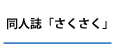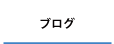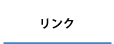2025年4月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:4月20日(日)
- 例会出席者:9名
夏の日の午後
どこか、励まされるような小説になっていて、なんとなくうれしくなる作品です。うれしくなるというのは、わからないのですが、なんとなく事件がハッピーエンドで解決するような予感がするのです。それにしても、作者の書かれる文章がとても滑らかに書かれていて、いつの間にか上達したのだろうかと、改めて感心しました。切々とした文章です。なおかつ、その滑らかな描写の向こうに、「明るい予感」が見えないのだけれど見える、そのように感じさせるものがあって、それが意識されての結果なのか、一生懸命に表現したらなのか、どうも断定はできませんけれど、格段にうまくなられたということを、読んでいて感じました。作品の構造なども、なるほどと感心させられます。さて、この後の後編でどのような展開になるのか、楽しみです。
わたしの家族
『わたしの家族』というタイトルの作品で、登場するのはママと、二人の姉妹=「ゆあ」と「ひかり」なのですが、ママと離婚したパパは別の家で暮らしています。別の家とは、パパの生まれた実家で、そこにはパパとパパのお父さんが暮らしています。離婚したあとの子供をどちらが引き取るかは、巷ではよく聞かれる話です。なかなか解決困難なことなのですが、よくよく考慮し、考えてみると、なんとなく作者は「問題」をすでに解決させてしまっているのではないでしょうか。「ゆあとひかり」は、ママのことはママで、一方のパパのことだってパパなのです。離婚したのはパパとママで、「ゆあ」と「ひかり」にとっては、極端にいえば関係ないのです。授業参観にパパとママが一緒に来ることはないでしょうが、気持ちは双方につながっているのでは……。
みんなの外
意味深なタイトルですね。彼がいて、彼女がいて、いつもの課長にミスを指摘され、空は青空、夕焼けになり、暗くなり、夜。仕事を終えて家に帰ると妻が迎えてくれて、家に帰ったという人心地がつき、それで、そういったことと交流することなく、そうしたものを他世界、異世界の中の個、と意識させられる強制。〈此処〉と〈其処〉にある超えられない境界……。こうした作品・文章を書くって、まったくの新しい世界に入って行ってしまうようで不安なのではないか。もっとも「面白い」と思って書かれているとしたら、それは幸いですね。ところで、ここに来ての米井さんの作品には、質的な向上を感じています。単に、奇想天外な作品を書かれる方だと思っていましたら、しっかりとした地盤を築き、なにかしらを視る目を持ち始めています。
四月の雪
不思議な作品ですね。私は大学を卒業して、浪人することが決まった女子高校生の家庭教師をすることになり、彼女が一人暮らしをしている部屋まで行くのです。と、なにやらキチンとしない感じで物事が、まるで勝手に進んで行くのですが、このことって、このこと自体がタイトルの『四月の雪』そのものなのではないかと、へんに感心させられました。まあ、普通なら、「四月になって桜が咲く」が一般的なのですが、『四月になって雪が降る』では時間が逆回転しているようではありませんか。そうしたことって、作者の意図です。なぜかはわかりません。うがった見方をすれば、「四月の雪」は「死月の雪」なのかもしれません。作品全体に流れる時間は、上から下へ、とか、現在から未来へ、とかではなく、なにもかもがランダムな「生」を帯びています。
追悼・北上遥
詩人の旅立ち
北上遥さんを送るに際して、『詩人の旅立ち』としたのは、関心がないようでいて、実はとてもよく見ていたのだなあと、つくづく思います。確かに、鈴木さんはSKをSKさんとしてみていました。
鈴木志津子さんとの思いで
確かに鈴木さんは聡明で、しっかりした女性でした。嘘が言えない気性の女性です。話が盛り上がらなくて落ち込んだりしていると、その場の雰囲気をいとも簡単にかえてくれる人でした。
アンとダイアナ
作品を読んでいて、なんとなく鈴木さんと小田さんが入れ替わったように感じました。それって、ちょうど末尾に書かれていたように、「アンとダイアナ」のようだなと思うのです。お二人が自分のことをアンだと想定していたとか。けれど思い返せば、アンの利発さや物怖じしないところなどは鈴木さんだと。いいえ、(アン+ダイアナ)=(鈴木+小田)でしょう。
遥さんとのこと
酷くはないのだけれど、不眠に悩まされ、散歩を心がける習慣をもった。公園に行くたびに会う女性といつしか会話をするようになり、公園通いの交際みたいな形ができてきます。こうした道筋の描写が作者はとても巧みです。いろいろな出来事はあるのでが、その描写はふわっとしていて、ふと消えるような感覚なのです。どこにも出っ張るところがなく、足らないところもなく、「透明で平たい、空間の中で、なんとなく自分の旅路を思っている。」なんて、見事です。
永井荷風 女性とお金 13
連載13回目ですね。すごいなと、ただただ感心するばかりです。永井荷風をここまで読んで、それで永井荷風とはどんな人間だったのか考えてみても、よくわからないのです。家にも執着しないし、女性にも、あるいは男友達に対しても、いろんなことにとても淡泊な感じをうけます。住む家があって、財布にはそれなりの金が入っていて、女のいる場所に行きたければいけるし、家に拘るならば建て替えもできる。そんな永井荷風を考えると、なぜか、寂しい人間を思わざるをえません。荷風の家は、高台にあり、崖の下には貧しい家並みが続きます。これって、まるで天国と地獄みたいです。もしかすると、この〈天国と地獄〉をじっと見つめることが好きだったのではないか、変に、想像してしまいます。このシリーズが始まったころ、『女性とおかね』というタイトルは変なのではないかと思いましたけれど、シリーズを経て、それが気軽であるのだけれど、その軽さこそが人間の本質なのかもなんて、少し考えるようになりました。
なゐ
『なゐ』は「地震」の古語だそうですね。関東大震災を深く思考したら、その古語である『なゐ』まで届いたのでしょう。最初に登場させる歌は『大地をば愛するものの悲しみを嘲める九月朔日の天』という与謝野晶子の作品でした。与謝野晶子、その夫の与謝野鉄幹、番町に住んでいた泉鏡花、「瑠璃光」からの三首。そうして、『鉄幹と晶子』というように作品の軸を立てます。『源氏物語』。 そして『文化学院』。この章は書くべきことが沢山あり、それなりのページ数をとっています。人はよく「絶望した」と言いますが、それは内面的なことで、とてつもなく広域でおこった外的な地震にたいしての衝撃はいかほどのものなのか。与謝野晶子と与謝野鉄幹の、その後のことを思うに、体にしみついた地震の揺れのようなものを感じさせられます。与謝野晶子は歌人として成功した。与謝野鉄幹は文学的才能を中絶させてしまった。 作品から、幾筋かの人間関係、生き方の個性、田舎と都会、川と町、ある意味で全体がスケッチされていて、作者の「目」の広域度には感心しました。