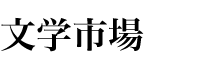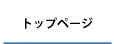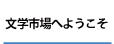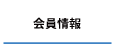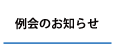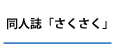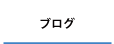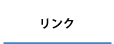2025年3月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:3月16日(日)
- 例会出席者:8名
曼殊沙華
導入部分が圧巻です。僕と母と姉は岸辺にて出てゆく船を見送るのです。船には父と二人の兄が乗っています。そうして……戦後の「今」が幕をあけるのです。戦後の貧しい時代ではあるが、明るい、光が垣間見えてきています。タイトルの『萬殊沙華』は、そうした時代の錯綜を象徴した華なのでしょう。今日子ちゃんはロシア人とのハーフです。戦後の大変な時代を生き抜き、ミハイルさんは82歳でなくなり寿枝伯母さんは101歳の天寿を全うします。その時代の彩りをそれぞれが生き抜いたのです。この作品が実話に基づいたものなのか、創作なのかわかりませんけれど、実話なのだと思います。戦争は大変でしたし、その後の復興にはまた涙ぐましい物語があります。
ブルーモーメント
不思議な作品だなと感じました。ストーリー的にはあまりリアルティ―がないのです。でも…なのです。ありえないことなのに、そのありえない理不尽な出来事に、不思議な納得感が現れてしまうような糸口があるのです。男は妹と心中して、妹だけをあの世へと行かせてしまった。そして今、その男は姉と結婚している。海は青いし、空気も青い、部屋の壁も、テーブルも、青い色彩に塗られているのです。姉も、私も、彼も青で、すべてが青に塗られているのです。死んだ妹に変わって結婚した「姉と男」。私には納得がいかないのです。「静かではいられない時間があるのだ」「飛行機はもういなかった」と、作品は平穏な落ち方をしつつ、危機は…まだまだ定まらないのでしょう。
花の万華鏡
「花の万華鏡」というタイトルつけた詩なので、楽しい詩なのかと思いきや、とてもシリアスな作品なのでびっくりしました。「盗人が正義を持ち出して」語るのですが、その語りはコロコロと転がって行きます。昨日からの緊縛、無花果を置く、感覚は自分のもの、僕の中に眠る君は、……詫びたいと思う、のです。さてはて…です。僕の内部に君の存在が………苦しむのは自分ばかりではない、のですが、苦しむのは自分ばかりではない、と、微妙にストレートです。返っていく、それが神の理屈だ、と審判はくだります。末尾の長い三行は、作者の結論なのか、述懐なのか、そして「僕は一つのパイを独占しているのだ」はやっぱり意味深です。
「心」を見つめて
この作品を読んで、いろんなことについて考えさせられました。南無阿弥陀仏にしろ、こんにちはにしろ、さようならにしても、挨拶の言葉って一期一会を伝えていて、ずっと一緒ですよ、の約束みたいでとてもありがたいです。でも、こうした難しくない言葉って、うっかりすると大事にされなくなってしまう場合があります。そして一度忘れてしまうと、なかなか思い出されません。なぜなのか。日常的に使い、ありがたく思っていたのに、わすれてしまうとなかなか思い出せないのです。東大寺茂さん、特に「東大寺」という名前から、とても知性の立つ方なのだと先入観をもっていましたけれど、そうではない、人間が大好きな方なのだと、この作品に接して実感しました。
続。ひょんなことから
作品を読んでわかりますように、北上さんはとても強い方です。女性に強いというのは誉め言葉にならないそうですが、北上さんに限っては言葉のとおりなのではないかと自負しています。どうにかなるわよ、と言い、前に向かって行動する姿は頼もしいです。作中での「癌を患って1年」は、この部分だけが意味不明になって受け取れないのです。同人誌を長いことやっていて、頼もしいと感じた女性は鈴木さん(北上遥)だけでした。笑顔しか記憶にありません。『せいぜい、歩行器を頼りに街歩きをすることで、理解を深めてもらうとするか』が、鈴木さんの書き納めとなりました。小沢一郎を後援会長として支えたお父様の根性を受け継いだ北上遥さんの書き納めの文章です。
永井荷風 女性とお金 12
『永井荷風 女性とお金 その12』楽しく読ませていただきました。それにしても、これだけの作品を書くためには、大変な労力と資料集めに翻弄されたのではないでしょうか。感謝、感謝です。作中にて、美人芸者のいるおすすめの土地が紹介されていて、その一番に「柳町」とあり、それは我が家から5分ほどのところにありまして、へぇーと感心したしだいです。確かに、隅田川のほとりで、神田川が隅田川に合流する地点でもあり、地の利があるのでしょう。柳の風情が色っぽいです。もっとも、当時とは異なって、そうした遊び場の面積は縮小されてしまっています。永井荷風って、一筋縄でも、二筋縄でも、三筋縄でもいかない、破天荒な作家なのだとつくづく思います。
隠れ里
タイトルが『隠れ里』となっていて、隠れ里が描写されている作品なのかと読んでいきましたけれど、ひとつ、またひとつと、かえって里の姿が現れてくるような作品で、作中から共感する事柄などを得て、生きるとか、生活だとか、血のつながりなど、数々の風景の美しさを堪能させられる作品でした。〈しっとりと小さな両手に平屋と庭が納まっていく感覚があった。ようやく竹田さんの平屋に認められた〉の一文は、とても幸いな心境でしょう。また作品に二重構造になった視点を感じました。小学校5年生の陵平の視点と、大人になったところの陵平の回想のような視点。竹田さんの家の周りの描写を丹念にされたのは、記憶の永遠を刻むためなのか、とても感動しました。
太陽ジャイアンツ 6
とても楽しまれて書かれていて、その点では好感しています。でも、ふっと、以前書かれていた作品を思い出してみますと、以前は色んなことが盛り込まれていたように思うのですが、いかがでしょうか。微妙です。今が盛り上がりの真っ最中なのであって、やがて何らかの着地点となるのかもしれません。それに、ジョニーさんはホントに野球が大好きで、それを小説で実践されているのかもしれないなあと、想像しています。もしかすると、高校野球クラスのレベルの高いところを念頭に書かれているのかもしれません。いずれにしても、以前のような人間関係を中心に置いた「野球小説」だと、楽しいです。
岩
不思議な作品で、うまく全体をつかめません。整合性はありませんが、なんとなく感じたのは、岩に閉じ込められた世界といったような感じです。そのことを登も、居酒屋の店員も、客も、誰もわからないのです。このような状況って、わからないゆえに、その話の尻尾もつかめないという世界、なのでしょう。向こうからいらっしゃって、こっちに来た。その「向こう」とは現実の人間社会で、「こっち」というのは死者の世界なのです。《明日の仕込みに備え、電気を消した》は、かなりの気配りですね。もはや登は他界した人間で、光があると返って物が見えないのでしょう。よく見えるように《電気を消した》のです。ちょっとハッとさせられました。