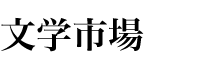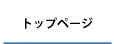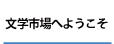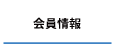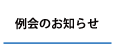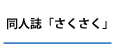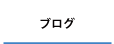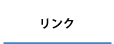2022年6月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:6月19日(日)
- 例会出席者:10名
ブドウ栽培の記
……八年前のことを思い出そうと、……と園芸日誌をのぞいてみたのが、この『ブドウ栽培の記』の八年間です。シャインマスカットとの出会いに辿り着いた経緯は、読んで行くと、どことなく男女の恋心の顛末のように感じられて、こちらもわくわくしてしまうのが不思議です。いつぞや、文学市場の「合評会」に合わせて花や葡萄を何種類も送っていただき、集まった皆さんで花も葡萄も堪能させていただきました。また、個人的にも……。関東平野の土と、利根川が運んだ砂がミックスされた大地に実る様々な収穫物は格別です。それにしても、葡萄と一口に言ってしまいますけれど、いろんな種類があるのですね。葡萄の見た目は、やや乾燥した土地に育つ果樹だと思われるのですが、それを、そうでないところでも育つように品種改良をして流布させる、人間ってすごいです。こうした『ブドウ栽培の記』を書かれる酔翁亭梅琴さんのチャレンジ精神こそ、すごいです。
天国と地獄
タイトルの「天国と地獄」が、ほんとうの天国と地獄になってしまうのではないかとワクワクしました。というのも、書かれた文面からご夫婦の息遣いが窺われたのです。なんと言いますか、若さが伝わってきました。まずは天国のことですが、さすがは航空会社の社員だけあって、天空を舞うパラセーリングを怖がる様子もなく、屈託なく楽しむ光景は爽快です。行きはよいよい、帰りは怖い…で、地獄めぐりです。もっと良い石を、よりよい石をと、つまりは値段のはるドアへと招かれて、そして部屋へと入る…、こうした初期の段階で普通は震え上がってしまうものですが、《この野郎!》なんて怒鳴りつけることができるなんて、当の宝石商でさえ度肝を抜かれたのではないかと思われます。ずいぶんと楽しい旅行になったのではないでしょうか。特に奥様にとっては、夫の真価を見極めた掛け替えのない旅行となったことでしょう。
フランス外人部隊
今回の『フランス外人部隊』は、戦後の様々な出来事が盛り込まれていて、時代の推移みたいなものを味わうことができました。また、戦後のこととなると妙に親近感を持つのですが、世界には解決不能な問題がまだまだ山のようにあるのですね。アルジェリアに駐留している誠が、ゲリラに襲撃される場面での瞬間、瞬間の描写はみごとです。「早く、早く……」「早く、早く……」と無意識の誠の叫び声が、誠が発し誠自身にも聞こえてくるのです。夜の闇の中に敵が見え、ハエが見え、吉祥寺の下宿が焼け、立川が焼けた、見なかったものさえ見えてきて「早く、早く……」と、命のある瞬間を確かめつつ、命をつなぐのです。それは立川にいるだろう峰子に対しての魂の電信であるでしょう。第二次世界大戦が終わる、その幕が下りのですが、気が付くと新しい幕開けとなっており、味方もいるけれど敵もいる、そしていつもの世界があるのです。
夏キノコ
タイトルの『夏キノコ』が何を意味しているのか考えてみました。でも、しっかりとした考えにはいたりませんでした。おそらく冒頭の「夏のキノコみたいに悪目立ちばかりしやがって」とどやしつけられた、その〈夏キノコ〉で、まだ新入社員を卒業していない「修一」自身に投げ掛けられた先輩からの言葉でしょう。修一はプロパンガスの業界紙の社員で、前に出よう、前に出ようと頑張るのですけれど、なにやかやと、80年代、90年代を過ごし、2001年、2011年3月11日へと、修一の会社員時代のことが振り返えられるのです。会社を退職して、街歩きを楽しみ、やがて高尾山登山の魅力にはまるのです。高尾山は多種多様な植物が自生している山です。広葉樹もあれば針葉樹、落葉樹と、植生は世界一だそうです。また、山頂からは正面に富士山が見えます。富士山まで行くのはたいへんなので、江戸時代、高尾山からでも富士山詣でができるように整備したのだとか。
月と階と塔
村上春樹の『アンダーグラウンド』って、この《月と階と塔》みたいな作品なのだろうかと、ぼんやり考えてみました。読んだことがないので、考えるといっても頭の中に浮かぶものもありません……。月とは黄泉の国。階とは、その黄泉の国にいくための一歩。塔とは卒塔婆。その卒塔婆をトロフィーというのは洒落た表現ですね。『月と階と塔』には時間も空間もありません。では、作品に登場する[東京][2001年][2011年][…時間の経過]などなどはなんでしょうか。階段の音、月光の肌に触れる感触、それらは在るものであり故に単に在るのです。双曲線が交わっているだけのモノです。淡路大震災があり、サリン事件があった年初に、文学市場は誕生しました。その後、東日本大震災があり、原子力発電所の爆発の映像もテレビで見たのですけれど、そうした諸々って、小説『月と階と塔』とイコールでつなぐことができるような気がして、おしなべて今です。
空き家
久方ぶりに〈鈴木節〉を堪能させていただきました。こうした作品って、作者が元気でなければ書けないので、ということは作者が元気だということで、作者が元気なのと作品がおもしろいのと、二重に楽しめます。田舎には貧しい家の子が豊かな家に養子に入るというのは、よく聞きます。実際には少ないのでしょうけれど、話題の少ない地方では格好の噂話のネタで、何度も語られる故、なにか沢山あったように感じられるのでしょう。地元の名家に養子に入り、東京に出ている美那子。落ちこぼれであったのに、まあ、立身出世(?)したゴロー。東南アジアからの出稼ぎ家族。昔だったら役者が異なったのでしょうが、現代は現代、まさに今っぽい登場人物たちでてんやわんやです。貧しい時代があって、信じられないような豊かな時代が過ぎて、すっかり疲弊してしまった地方なのですが、美耶子がいてゴローがいて、フィリッピンからの客人もいて、故郷はあります。
しじま
各パートごとに一つの流れがあり、別々のものとなってその場に存在し続けるような、全体の構成がなされています。とはいえ、生身の出来事は祐二と祐羽なのですが、それがどんなものなのかは謎です。そもそも不思議な取り合わせでしょう。祐二は東京の高校を目指し、反対に祐羽は東京から千葉へとやってきたのです。祐二と祐羽の思いは鮮明に描かれるのですが、すでに幼い頃、祐羽は佑太と儀式上での結婚をすませて、すべてうまくいっていたなら否定することもできるけれど、裕太が死に、祐羽が亡くなった今、あらゆることが真実にならざるを得ないのです。この作品は作者の集大成でしょう。まだ、完成された作品だというわけではなく、道筋が明確になったということです。もちろん、ミイラ取りがミイラになってはいけません。新しい題材等々にはチャレンジしていただきたいなと思います。作者は、全ての登場人物に愛情を注いていて、好感します。