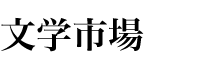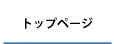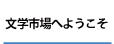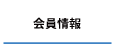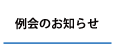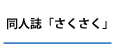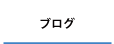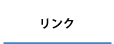2020年11月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:11月15日(日)
- 例会出席者:10名
アタシね~由比子のヰタセクスアリス
毎回、たのしく読ませていただいています。シリーズとして書かれていて、連続性はないのだと読んではいますが、なんとなく、前回書いていたものと、その次に書かれたものが矛盾するような書かれ方があると、不自然に感じることもあります。「アタシ」が何歳の頃だったかを記するとよいと思います。そうすると前後関係もよく理解できます。「アタシ」は不思議な女性ですね。性的には貪欲で、酸いも甘いも裏の裏まで熟知していながら、心はウブです。こういったことを一言であらわせば、性的巡礼者でしょうか。巡礼者ですから、心の闇は深いものがあると感じています。そこを軽いタッチで書かれていて、「アタシ」は何事かにさ迷うのです。「アタシには/次回はない」は、なぜそうなのだろうかと考えさせられます。肉体的には満足したけれど、心の部分では満足しなかったということでしょうか。ここのところ、いつも2頁ですが、もう少し長く書かれたら、いろいろと由比子を表現できるのではないか思います。79号を楽しみにしています。
自分の部屋
稀有な作品です。タイトルの「自分の部屋」とは何か、を読み取ることができると俄然おもしろくなります。部屋とは、リアルな部屋ではなく脳内での自分の幻影のことでしょう。現れては消え、消えては現れる鼠。その鼠とは騒音のことでもあれば、まさに鼠の姿や形のことでもあります。P109下段12行目~18行目の描写は圧巻です。「虎の吠え声が、部屋に響く」は、襖絵の虎が吠えている描写ですが、鼠は震えているのです。この鼠とは「自分」のことでもあるのです。つまり、こうしてすべてが位相上の世界になっています。「外は暗く、部屋の中でだけ雨が降っている」と段落をつけますが、「外は暗く」「部屋の中でだけ雨が降っている」も迷路です。外の世界は暗くてわからない。自分の部屋には雨が降っていて困っている。のです。と書き進めて「錠剤」を飲むと世界が静かになります。「雨は降らない」「幽霊は、治った」のです。境界を持たない「自分」から、境界を持つであろう「幽霊」となり、「幽霊はぼんやりと、部屋の中の掃除をしている」のです。
チップは受け取れない
娘さん一家が、ご亭主の転勤によってニューヨークに行ったことが書かれています。現代ではよくある話なのですか、人間が生きていく機微みたいなものが丁寧に描かれています。娘さんがいて、アメリカ人と結婚して、小学校五年生と二年生の孫がいるのに、日本からアメリカへの転勤したあれこれです。日本人、アメリカ人という感覚が新鮮に感じました。娘は仕方ないにしても孫を心配するお爺ちゃんの気持は複雑です。とはいえ、すっかりアメリカに馴染んでいる孫娘を見て、一安心するのでした。奥様の登場場面が少ないなと感じていたら、最後になってパスポート紛失事件が勃発し、元来のといいますか、落ち着くところに落ち着いたという感じに締め括っています。空港の大男の係員の言葉、「私はアメリカ合衆国の公務員だよ。チップは受けとることなんて出来ないのだ!」には、感動しました。彼の上司の上司、一番のトップが民主主義のルールである選挙結果を受け入れないのに比べると、清々しい気持ちになります。
明るい未来
情報量がいっぱい詰まった作品かなと読みました。一段目は、コロナ禍の学校の休講のこと。二段目は北朝鮮からのミサイル発射。そうした状況下で展開していきます。「お願い」がやっぱりキーワードでしょうか。人がふいと死んでいく。なぜなのかわかりません。理由がわからないことほど、人間を不安にさせることはありません。人が死んでいく。まるで魯迅の『狂人日記』のような世界です。けれど、視点人物の「大輝」は狂人ではなく、〈よく見ている人〉です。周りの人が死んでいく状況を『明るい未来』というタイトルなのが不思議です。中学校で社会の先生から学びました。「人と人とがいる。その人と人がいる関係、間があって人間」なのだと。へえーとは思ったものの、ただそだけでした。もしかすると社会ではなく道徳の時間だったかもしれません。みごとなもので、この作品では、その「間」がきれいさっぱり除去されていくのです。だとすると「暗い未来」じゃないかと思うのですが、それは主観があればのこと、客観だけだと「明るい社会」なのか…。
わが愛すべき言葉たちの〈復権〉のために
私はある試験を受け、一次試験、二次試験とすすみ、三次の面接に臨みました。その時、面接官から質問されました。なぜこの試験を受けたのか文書で前もって提出していました。そこには、「私は大学を中退していて、就職先がありません。仕方なく二年間ほど土方に精を出していました」というようなことを書いたと記憶しています。この時、面接官は「土方」というものを理解できなかったようでした。今、「飯場(はんば)」に泊まりこんで、とパソコンに打ち込もうとしたら、もしかすると「飯場」も差別語なのか、出てこないのです。なるほど、そういうことなのかと、ちょっとびっくりしました。言葉にヒステリックに対応する、そのこと自体が差別を生みだしているのではないかと、思います。変に語気を強めたり、急にヒソヒソ声になるとかの振る舞いが、特定の人を差別してしまうのです。もしかすると、一般語の言葉として通用している「非正規社員」なる言葉も、ここのところ差別的に使われます。人間の品性が悪いと、よくならないでしょう。
オーロラ
オーロラのような物語です。10歳の女の子・スオミ、母、弟、村長、浮島に逃げた父などが、生きた登場人物です。なお幽鬼が登場しますけれど、こちらは存在するものなのかどうかはわかりません。幻想的領域での現れなのかもしれません。オーロラのように……。父が人を殺し、村の「お守り」を盗んで逃げてしまった。10年が経ってあの時と同じ様な不吉な予感が村に漂いはじめ、その父が盗んだ村のお守りを取返してくることを、村長から依頼されたのです。スオミは冬の嵐、空のオーロラのもと、湖をわたり浮島を目指します。氷面に写った自分の姿が、写す自分が動いたにもかかわらず、写った姿は動かないという、夢か現かわからない体験をします。幽鬼とも出合いますが、わりあいとスムースに父のもとに辿り着くことができました。大事な「お守り」なのですが、無造作に父から手渡されます。スオミが家に帰ると、すっかり母は変わっています。男を部屋に入れて…。人と人との間に、氷やオーロラが混濁して、全てが「個」になったような幕引きです。