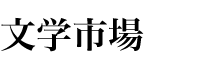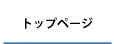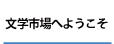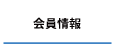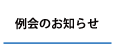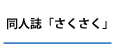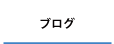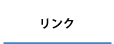2019年7月の例会報告
毎月、会長が報告して下さる例会報告です。
- 日時:7月21日(日)
- 例会出席者:15名
海月
いつも作者の作品には主語がありません。これまで気にしなかったのですけれど、なぜか、今回は気になります。きっとタイトルの「海月」がそうさせるのでしょう。新宿二丁目界隈にあるボーイ持ち出しOKの風俗営業の店でのマスターとの会話、一風変わったボーイの真尋のこと、美術の話、そうした海の底にでもいるような日常会話が繰り返されていきます。視点は海月にあるのかもしれません。とりあえず語り手たる「私」はいるのですが、それは作品を読む者に感じられるのであって、作中となるといなくなってしまうのです。大学の非常勤講師である「私」なのですが、わたしは漂っているだけです。マスターも漂い、真尋も漂うものです。それらを海月として描写しているのかもしれません。または、何者でもないもの、それが海月で、実質的な関係をもつことなく漂う有様を見ているようにも感じられます。杏子は存在する人間でしょう。もしかすると、夢を持っているマスターもいつか存在するでしょう。常勤講師となった有川は、大学に行く目的を持った真尋はどうなるか。雨は降って、雲間が切れて、日が射し、また雨が降ってきます。
リョウコちゃん 7
リョウコちゃんと原田くん、田中くんと私の、スポーツ大会での二人三脚の模様が書かれた作品です。スポーツはおおむね個人が競うものですが、綱引きや玉入れ、バレーボール等々、団体競技もたくさんあります。その中でも、二人三脚はもっとも少人数でする団体(?)競技です。文章の主語で例えれば、個人競技は「私の一人称」で、団体競技は「彼という三人称」、だとすると二人三脚は「あなたとの二人称」による競技でしょう。互いの右足と左足をきつすぎず・ゆるすぎず結んで、呼吸を合わせて走らないと転んでしまいます。それなのに原田くんと田中くんは、なぜそれができなかったのでしょう。肝心のリョウコちゃんと原田くんがどのように走ったのか書かれてないので、よくわかりませんが、互いの足を二十センチ離して結んだことから察しはつきます。何度も転んでしまったのではないでしょうか。教室に戻った先生の言葉から、このクラスの先生は、とてもよい先生だったのだと思いました。大人になった原田くんや田中くんが、この二人三脚のことを思い出すことがあるのかどうか、気になります。……思い出してくれるといいのですが。
ひまわり園
老いというのは難しいです。もっとも、簡単なことなのかもしれません。簡単なことなのに、「考えたくない」ので考えない、なので難しいのでしょう。P222下段に「気持ちは若い頃と変わらないままである」とあります。小学校、中学校、高校(私は特殊のところに行っていたので、高校ではないのですが)、大学、と過ごしていたころと現在で何ら気持に変わりはありません。たぶん、皆さんもそうなのではないでしょうか。それにもかかわらず、「時間を経た」という実感だけは現実にあります。施設にて、自分と隣り合わせているような方たちと接していると、不思議な感覚になるのではないかと思います。幼稚園のころの「先生と園児の関係」が、施設での「看護職員と利用者」では逆転した関係になっているのです。もっとも、先があるかないかの大きな違いがあります。さまざま出来事を書いて、タイトルの「ひまわり園」に括ったのは、成功していると思いました。「ひまわり園」とは意味深な象徴になっています。ひまわりの花の造形は豊かな空間をイメージさせます。また「ひまわり」には時間をイメージさせます。……「日が回る」のですから。
じいちゃんの恩返し
文学賞に絡ませて「じいちゃんの恩返し」を書いた作品です。創作に邁進している者にとって、文学賞とか同人誌は、そのこと自体を表現してみたいと思うテーマになりえます。メタ文学的な作品とでも言えばよいのでしょうか。ただ、そちらの方には深入りせず、明るく前向きな作品にまとめています。「鮎川哲也賞」を蒲田推理文学会の現在の代表である山内加奈さんが受賞、「僕と綾香」の結婚話、綾香の祖父・松沢繁一と志村道子とのおまけのような結婚、これらがドタバタ劇のように進行、楽しませてくれます。ただし、エンタメ小説を単におもしろい小説ととらえてしまうと成功しません。エンタメを書くにしても、作者の見極めは必要です。エンタメ小説の構成と文体を考えて書くことです。「蒲田推理文学賞」は「北区・内田康夫ミステリー文学賞」から拝借したものだそうです。この賞に、文学市場の会員・新開拓海さんは二度、最終選考に残ったことがあります。その新開さんから、佐藤さんの作品はよくまとまっている、あとは校正をするだけだ、とのアドバイスをいただいております。明るい小説を書けるということは、現代において、貴重な才能です。
戊辰の空へ・血まみれ芳年江都絵図・第一図 髷切り半次郎
江戸の職人は段取りを大事にしますけれど、それにあやかったような新シリーズの幕開けとなっております。下働きの文吉が飯の種を絵師・芳年にもたらすところからはじまります。そうしておいて、当時の江戸の殺伐とした世相を描写するのです。亜米利加との和親条約、江戸から畿内にかけての大地震、その翌年の飛騨地方の地震、夏の陸前、ひと月後の遠州灘地震、そして有名な安政地震です。戸籍のない角付け芸人や物乞いが跋扈し、いかにも幕末といった舞台ができあがっていくのです。そこに絵師・芳年や目明し弥平、新内節の門付けお容と、役者がそろいます。お容の手柄で、髷切りのずんだら坊を突き止め、同心・逸見宗助等は髷切り犯を奉行所に同道することになり一件落着になるのですが、なんの解決にもならないのが幕末の幕末たるゆえんです。髷切りのずんだら坊の名前は「中村半次郎」、幕末最強の人斬りだったのです。西郷隆盛の最も信頼する朋友でもあります。ということで、つかまえたらすむわけではなく、すぐに解き放ちになってしまいます。この時の中村半次郎を芳年はどのような絵図にしたのか、書かれてないだけにワクワクします。